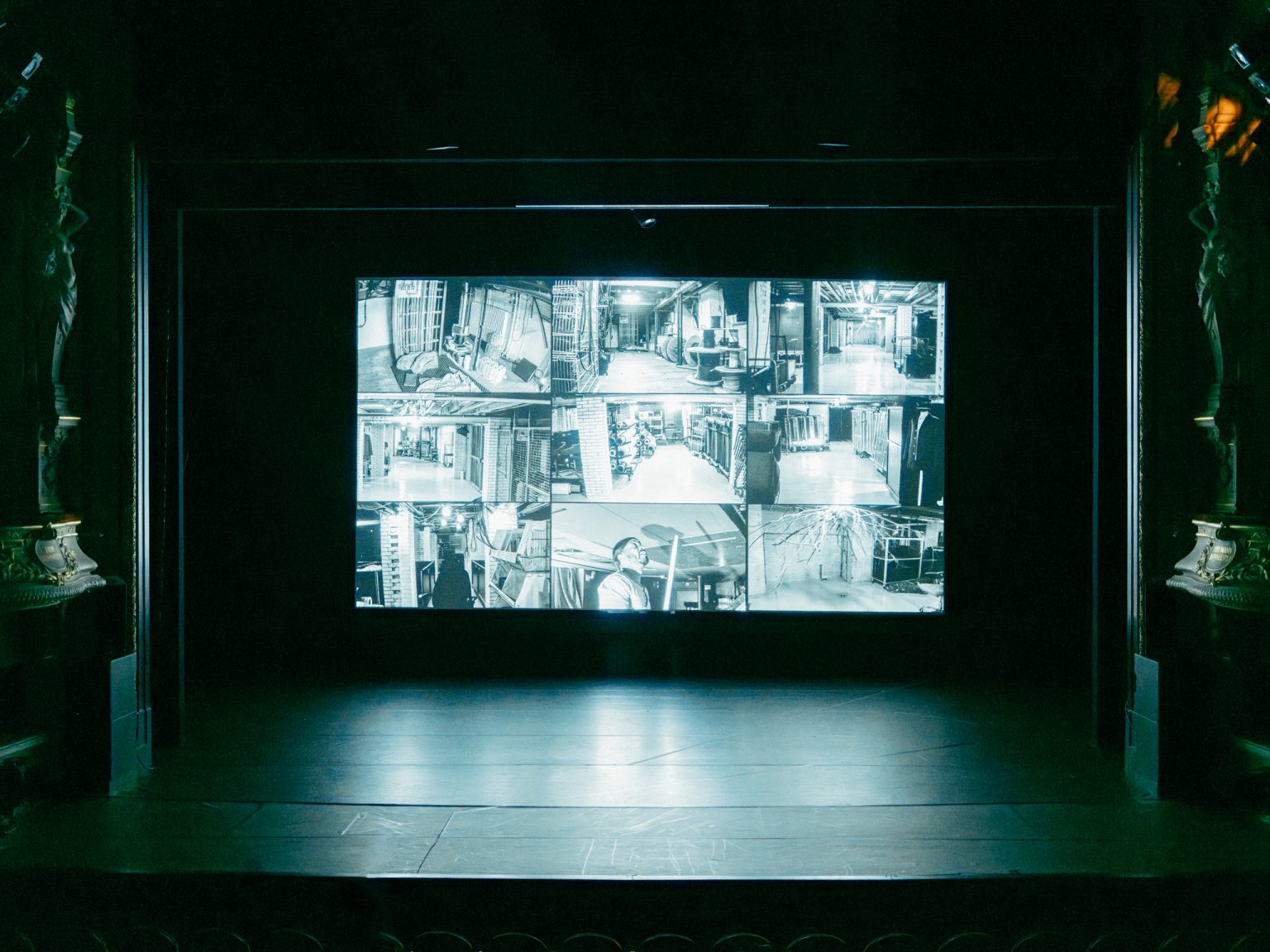「何世紀にもわたり、私たちは自分たちが囚われてきた構造的な悪を名指ししてきました。ただ問題は、それを他の人々が知ろうとする意思があるのかどうかです」
先駆的な研究書『Scenes of Subjection』(1997年)を発表して以来、アメリカの研究者、サイディヤ・ハートマンは、奴隷制の「その後」をいかに理解するかという認識の枠組みを抜本的に転換してきた。『母を失うこと―大西洋奴隷航路をたどる旅』(2007年)や『奔放な生、うつくしい実験』(2019年)といった著作や数多くの論文において、彼女は帰属と追放のあいだに広がる閾的な空間、すなわち、アフリカから遠く切り離されながらも、その喪失によって形づくられたアフリカ系アメリカ人の立場を理論化してきた。欠如や沈黙、抹消によって刻印された奴隷制のアーカイヴを読み解くため、ハートマンは「批評的創話(critical fabulation)」という手法を編み出した。それは、アーカイブ研究とナラティブ的想像力を交差させることで、記録の上ではほとんど顧みられず「些細な」歴史的行為者として扱われてきた人々の生に潜在していた可能性を回復しようとする試みである。ブラック・スタディーズやフェミニズム理論から、文学、美術に至るさまざまな領域において、彼女の著作は欠くことのできない参照点となっており、主体性や抵抗、人種資本主義という継続した構造をめぐる私たちの思考そのものを更新してきた。
彼女の最新作《Minor Music at the End of the World》(2025年)は、オランダのハートヴィヒ美術財団によって企画され、サラ・ベンソン演出のもと上演されるコラボレティブなパフォーマンスという形式を通じて、批評的創話を新たな次元へと押し広げている。本作は、20世紀における人種、民主主義、ブラック・リベレーションをめぐるきわめて重要な知的言説を担ったW.E.B. デュボイスのSF短編作品に着想を得ている。『黒人の魂』(1903年)という代表作で知られるデュボイスは、1918年のスペインかぜパンデミック後、地球に残された最後の黒人男性を描いたSF短編『The Comet』(1920)も著しており、《Minor Music》の思考的基盤はこの物語の示唆によって形づくられている。作品は三つの章から成り、第一章はハートマンの論文「The End of White Supremacy」(2020年)および「Litany for Grieving Sisters」(2022年)に基づいている。第二章「Dead River」は本作のために新たに書き下ろされており、第三章は、アーサー・ジャファの映像作品《Aghdra》(2021年)をリミックスしたものだ。こうした構成を通じて、本作は多声的で協働的な思考のかたちを立ち上げている。アンドレ・ホランドやオクウィ・オクポクワシリらアーティストによる言葉と身体のパフォーマンスを通じて、本作は生態系の崩壊や権威主義の台頭、人間の代替可能性、そして学術的・芸術的自由の解体によって特徴づけられる現代において、いかなる住まい方(dwelling)や拒否、集団性が立ち現れうるのかを問いかける。ArtReviewは、《Minor Music》のワールドプレミアを目前に控えたハートマンに取材を行った。

理論から実践へ
ArtReview あなたは《Minor Music》を「奔放者たちの合唱(chorus of the wayward)」と表現していますね。そこに、これまであなたが論じてきた「逃走的な存在(fugitive being)」の議論と響き合うものを感じます。今回の作品はどのような内容で、どのような意図で制作されたのか教えていただけますか。
サイディヤ・ハートマン この作品は三つの章から成り立っています。第一章は、現在と、1世紀前に『The Comet』を書いたW.E.B. デュボイスを結びつけるものです。デュボイスは作中で、人種化された暴力や隔離、そして資本やエリートによる苛烈な支配によって規定されたアメリカを描いています。また、1918年のスペインかぜパンデミックの影もそこにあります。人種秩序の終焉を想像するとは、いったいどういうことなのでしょうか。この「終わり」は2020年に始まったものの、そこでいったん停止したと言うこともできるかもしれません。権威主義や資本主義、白人ナショナリズム、さらには奴隷制や入植植民地主義の英雄たちを称揚する風潮は、むしろ現在において、いっそう強まっています。では、改めて、この秩序の終わりを想像するとは何を意味するのでしょうか。その問いに向き合うために、《Minor Music》はデュボイスのテクストと私のテクストの間を行き来します。そこには、気候危機がもたらす、別種の「絶滅」の脅威ー世界の終わりのもう一つの次元ーも重ね合わされています。
AR テキストは、他者に解釈されるとしばしば作者の意図から離れることがあります。そんななかで、パフォーマーたちがあなたのテキストを声や身体で表現する様子を見ていてどのように感じましたか。
SH 『The End of White Supremacy, An American Romance』(ハートマンが2020年発表した、デュボイス『The Comet』に関するテキスト)と『Dead River』(2025年、オクウィ・オクポクワシリがブリア・ベーコン、オードリー・ヘイルズ、AJ・ウィルモアらのパフォーマーと共同で制作した作品)のテクストは、それ自体が共同制作の作品であり、さまざまな理論家や作家の知見が織りなす、いわば発話の連なりです。それこそが、この作品の重奏的な性質を形作っています。たとえ私の名前が記されていても、多くの声が共に存在しているのです。パフォーマンスはテクストを単に再現するのではなく、それを発語し、かたちづくることでその意味を豊かにし、変容させます。そこにこそ、プロセスが持つダイナミズムがあり、テクストはつねに作り直されていきます。だからこの作品は進化し続けるし、その協働的な性格を私はとても大切にしています。私は数ある担い手の一人にすぎません。アンドレやオクウィのような、卓越した技量と表現力を持つパフォーマーたちがほかにもたくさんいます。私は、文の力や段落のうねり、ページが生みだすドラマといった、言語に特別な感受性を持っています。しかし、自分の言葉が他者によって発せられるのを聴く体験は、まったく別のものです。それらは〈他なるもの〉へと変わっていく。それはまるで言葉が自分の所有を超えていくような、とても美しい経験です。


強調しておきたいのは、私が書いたものは戯曲ではないということです。これは、上演される言説、あるいは多声的な発話なんです。オクウィのパフォーマンスでは、長時間にわたる身体的に負荷の高い動きと声をを伴い、演劇の慣習的な枠組みに抗っています。登場人物中心の演劇とは異なり、言説をいかにして演じ、身体化しうるのか ー それが問われているのです。そしてまた、クラシックな演劇訓練を受けたアンドレが、批判的思考を血肉へと変え、概念を「地球上に最後に残された黒人男性」の自伝へと作り替えていく瞬間には、魔法のようなものを感じました。こうした世界との出会いは、私たちの存在に亀裂を生じさせ、思考に根本的な変化をもたらすのです。
ある時代の終焉
AR 集団的な学びや協働のあり方を描き出すそのイメージが、とても印象的です。フェミニストで脱植民地主義の研究者フランソワーズ・ヴェルジェスが、以前ArtReviewで、協働的に美術館を再構想することが重要であると語っていたことを思い出します。ただし、ヴェルジェスは、そのような試みが制度に取り込まれてしまう危険性も指摘していました。パフォーマンスは、その傾向に抗うことができると思われますか。
SH パフォーマンスも、もちろん切り離されたり再構成されたりすることはありますが、美術作品のように価値が付与され、個人によって収集されうるのとは異なります。権威ある機関との関係は常に緊張を孕んでいます。たとえラディカルな志向をもつ作品であっても、逆説的に制度の再生産に加担してしまうことがあるからです。今のアメリカでは、《Minor Music》を国内で制作するのは非常に難しいでしょう。黒人女性、奴隷制、フェミニズム、ジェンダー、反黒人主義、気候、環境、資本主義といったテーマを扱う作品は「反米的」とされ、禁止されたり、資金が剥奪されたりしています。そうした作品をつくる人たちは「内なる敵」とみなされ、マルクス主義者や共産主義者の逮捕を求める声まで上がっています。アメリカは今、権威主義的な時代に突入しています。それは、復古主義的かつ白人至上主義的で、(ジークムント)フロイトや(マックス)ウェーバーのような西洋の正典的思想家にさえ敵対的です。多くの州立大学では社会学がカリキュラムから排除され、権力や格差の構造、支配や雇用の不安定さ、代替可能性、富の集中といった社会的差異を分析する批判的な枠組みが禁止されつつあります。こうしたファシズム的な権威主義の目的は、奴隷制社会を支えてきた価値秩序を復活させることにあります。すなわち、黒人の命を従属的で可換的なものとみなし、支配される者に対する搾取と支配によって未来を確保し、財産を持つ白人男性に固有の権利としての自由を再び中心に据えることです。現政権の価値観や見解に従わないものすべてに対する戦争が起きています。美術館から作品は撤去され、アーカイブは削除され、破壊されています。今、私たちは基本的な学問の自由そのものをめぐる闘争の只中にあります。私がアメリカで携わっていることは、流行を追うような類のものではありません。それは根絶の対象とされているプロジェクトへの関与なのです。

AR 世界秩序の終焉について考えることは、創造的であると同時に恐怖を伴うものでもあります。右派の論客から一般の人々に至るまで、暴力的な反発も目にしてきました。確かに、革命的な断絶の時代は血なまぐさく、不安定です。この作品はまた、喪失や不確実性──私たちがもはや現状のままでは生き続けることができない一方で、人種資本主義を超え、環境的にも健全な世界について、共通のビジョンが一つとして持てないという事実──にも向き合っているのでしょう。
SH 第二章は、まさにその開かれた問いによって構成されています。重要な座標が不明なまま、道を見出すとはどういうことなのか。人間の存在そのものもまた、開かれた問いなのでしょうか――私たちは、他の生き物の生命のための土台や通り道にすぎないのでしょうか。
AR それは、人間中心主義を手放すことも求めていますね。
SH そうです。「人間」の破壊的な性質――たとえば、パチンコから原子爆弾に至る「進歩」の歴史を考えてみてください。改革を試みは、しばしば別の秩序の暴力を生み出してみました。私は今のための、この瞬間のための実践に関わっています。ケアの集積や共同性を通して、被害を最小限に抑えつつ、別の住まい方・生き方を生み出す実践です。未来が保証されているわけではありませんが、実践は未来の確約に左右される必要はありません。解放運動を結果だけで測ろうとすれば、その意義を誤解し、成果を過小評価してしまいます。フランツ・ファノンは、植民地主義に抵抗した多くの人々が、その闘いの成果を生きて目にすることはできなかったと指摘しています。
家事としての革命
AR 私たちは、長期的な視点よりも目先の成果を求めてしまいがちです。たとえその変化を自分たちが目にすることができなかったとしても、その道を切り開くために、今、私たちのコミュニティではどのような関係性や実践を追求することができるでしょうか。
SH すでに多くの人々がそうした変化に関わっています。無償の学校や、金銭を介さない助け合いや物々交換、ラディカルなコレクティブや土地信託などです。また、権威主義的なプロジェクトと結びついた巨大資本を背景にしたテクノクラートの企業や、反DEIの方針を掲げる企業をボイコットすることで、拒否の姿勢を示している人々もいます。日常的な実践のなかには、制度に取り込まれずに機能するものもあります。もちろん、それが何を生むかについて保証はありません。私が学部生だったころ、私たちは皆、若き革命家になりたいと思っていましたが、教授の一人、ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァクにこう戒められました。「革命は家事のようなもの――毎日やらなければなりません」。革命は終わることなく、未完成のまま続いていく営みなのです。

AR 『Scenes of Subjection』で「倫理的傾聴(ethical listening)」について書かれていましたが、今回の作品にもその考えを取り入れていますか。この作品における「聴き手」とは誰でしょうか。また、観客にはどのような聴き方をしてほしいですか。
SH 切実な希望は、観客が「聴いてくれること」です。私は「The Frequency of Black Life」という講義で、黒人の生が音響的に立ち現れる諸要素について考察をしています。聴くことは他者の存在を前提とし、交換の場をつくり出します。本作では「マイナー・ミュージック」として響く音が、変化や、何かが失われた状態を示します。作品は、マイナーキー(短調)が担う批判的な役割を探求しています。それはメジャーや「正統なもの」(長調)へと踏み込むことではなく、不協和を孕んだマイナーな営みを受け入れることです。マイナー・ミュージック、マイナーな存在、マイナーな文学といったように。動きのスコアは不透明さと未完成さを受け入れ、サウンド・スコアや身体的パフォーマンスの振付が重なり合うことで、労働や世界についての複数的で分岐した視点を提示します。《Minor Music》は、集い、共に思考することへの招待であり、同時に作品を体験する者に、それをどう受け取るのか、あるいは受け取ることができるのかを問いかけるのです。
絶対的暴力
AR オンライン上の多くの論評では、この作品は主に黒人の社会的生における「声」と「拒否」を扱ったものだと捉えられています。確かにそれは一面ではありますが、人種化され、ジェンダー化された資本主義のもとで、私たちすべてが関わらざるを得ないグローバルな闘いとも、この作品はつながっているとお考えですか。
SH このパフォーマンスは、語り手がグローバルな資本主義システムのなかでどのように形づくられてきたかを考えるところから始まります。世界は一つのシステムであり、私たちの歴史は横断的につながっています。アメリカ帝国の影響力は、ここで起きたことが世界中に波及することを意味します。人種化、反黒人主義、植民地主義の構造はグローバルであり、それらを維持しようとする仕組みは互いに学び合っています。たとえば、ナチスはアメリカのモデルをもとに人種法を構築しました。ヒトラーはアメリカの人種秩序を称賛していたのです。「世界の終わりに存在するとはどういうことか」という問いは、共有されたものです。私たちは地球上のそれぞれの場所で、意識ある存在として、土地や時間をどのように生きるのかについてさまざまな考えを抱きながら、それぞれの形でこの問いと向き合っているのです。

AR 資本がさらなる蓄積を求め、多くの政府が権威主義的になるなかで、世界の人々の平均寿命や生活の質は著しく低下してきました。その時点で、左派の多くは階級や人種を超えた連帯意識が生まれることを期待しましたが、実際にはそうはなりませんでした。
SH 覇権的な世界秩序の中心で暮らす人々が、他の地域で何十年、あるいは何世紀もわたって抱えられてきた、存在をめぐる問いにようやく向き合い始めています。国家や権利に基づく政治の限界は、別の生のあり方を構想する必要性を示しています。アメリカ国家はもはや共同体を守る役割を放棄し、収奪的で略奪的な存在となり、その暴力は絶対的なものになっています。その一方で、民間による「解決策」が現れています。数十万ドルの資産を持つ人々は、自然循環型農法(バイオダイナミック農法)による農場を備えた環境配慮型の住居を購入し、自然志向の暮らしを実践することができます。代替的な生のあり方そのものが、すでに商品化されつつあるのです。
私の世界へようこそ
AR 大多数が気候変動の影響に直面する一方で、地球を再緑化するのではなく、一部の人々だけがゲート付きの居住可能なゾーンに住まうーその光景は、新たな形のアパルトヘイトのようにも思えます。
SH (イーロン)マスクや(ドナルド)トランプのような人物は、これまで暗黙のうちに伏せられてきたことを公然と言い放ち、一部の命が他より価値を持つという垂直的な秩序を擁護しています。このヒエラルキーはすでに自明のものとみなされています。リベラルな体制下ではその事実を覆い隠す必要がありましたが、今はもうその必要すらありません。使い捨てにされ、不安定で、代替可能な存在とみなされ、投獄される人々を隔離・排除するアパルトヘイト的な秩序が拡大し続けています。政策は露骨に富を上層に集中させています。黒人が市民権を得たのは、極めて遅れてのことでした。19世紀にヨーロッパ人が当然のものとして享受していた権利を、私たちが手にしたのは1965年 ー つまり、私が生まれてからの出来事です。私たち(黒人)の多くは、人種化された囲い込みと恐怖のなかで生きてきました。それが常態だったのです。多くのアメリカ人は、自国は例外的だと信じ、他国と同じ運命をたどることを想像できません。その結果、危機に対する切迫感が共有されず、何百万人もの人々が街頭で立ち上がるような政治的行動が生まれていないのです。

AR ある意味で例外とも言えます。覇権的世界秩序の中枢に位置していたがゆえに、他の地域よりも、この運命からしばらくのあいだ守られてきたからです。しかし、その暴力のあり方自体は同じです。では《Minor Music》がパフォーマンスを通して示唆しているように、想像という行為のなかには、どのような希望が見出せるのでしょうか。
SH 覆いはすでに取り払われましたが、現実に気づいた人々がすぐに変わるとは思えません。富や白人特権によって守られてきた人々が、初めて権利を脅かされ、不安定な市民的地位に直面しているのです。私たちはこう言います ー「私たちの世界へようこそ」と。私は、均質化しつつあるこの「共有された不安定性」の芽生えが《Minor Music》が終焉として描き出す人種秩序を解体することを願っています。しかしアメリカでは、自らが社会的に使い捨てられる存在であるという認識が、同時に白人ナショナリズムを活性化させる契機にもなっています。リベラルな論客たちは現在を例外的な事態として扱い、かつてアメリカが「平和を維持していた」とされる「黄金時代」― 彼ら自身の「MAGA的想像力」― に思いを馳せています。彼らはアメリカ建国を美化し、人種奴隷制や入植者植民地主義を無視したまま、トランプ主義に対抗しようと、自らの幻想にすがっているのです。特権を享受し、安穏な位置にいる人々は、リベラリズムが成り立たせてきた構造的排除を理解していません。
AR 国家から付与される市民権が、つねに例外やヒエラルキーを伴ってきたというこの認識は、「世界の終わり」において思考するための前提—すなわち、国家による人種化・ジェンダー化された承認の枠組みを超えた人間性について再考する契機となり得るでしょうか?
SH それは美しく、私にとって希望を感じさせる言い方です。アメリカにおいて「黒人であること」は構造的な位置付けであるという事実を、私たちは忘れてはなりません。それは、使い捨てにされ、理不尽な暴力や国家による恐怖にさらされ、人生の機会を奪われ、賃金体系や社会秩序の最下層に置かれる存在です。長い間、多くの黒人は自らを無国籍者のように感じてきました。マルコムXによる国連への請願や、ポール・ロブソンとウィリアム・パターソンが、アメリカをジェノサイドで告発した請願を思い起こしてください。デュボイスは、アメリカという国家理念を放棄し、亡命の地で生涯を終えました。何世紀にもわたり、私たちは自分たちが囚われてきた構造的な悪を名指ししてきました。問題は、それを他の人々が知ろうとする意思があるかどうかです。そして、こうした拘束を可能にしてきた知と権力の構造が、別の何かを生み出しうるのか―あるいは、存在や世界、地球そのものを根本から再考しなければならないのか、という問いなのです。
文=サラ・ジラーニ (翻訳=南のえみ)
サラ・ジラーニは、ロンドン大学シティ校の講師で、専門はポストコロニアル文学およびワールド・シネマです。